adding Dec '96
adding & Fixed Apr 1999
Tweet


[ Computer Unit の中身 --- 電気信号のお化け箱
[ その心臓 -- CPU
[ 管理媒体 -- Mother Board (M/B)
[ 記録媒体 -- Floppy Hard Disc TapeDisc MO CD-RW DVD-RW
[ 記憶媒体 -- RAM or ROM
[ 指示媒体 -- Keyboard or Mouse
[ 印刷媒体 -- Printer
[ 連結媒体 -- Modem or Ethernet-card or Router or ADSL
[ 取込媒体 -- SCANNER or Digital Camara
[ 表示媒体 -- Monitor
[ 媒体の連結 -- OS = MS-DOS & WINDOWS という System
[ 目的媒体 -- SoftWare or Application
[ MultiMEDIA へ
 |
[ Computer Unit の中身 --- 電気信号のお化け箱
Computer の心臓部は Unit 本体に納めてあります。HardWare につい
て書く事が多分、機械全体を知ることについても重要だと判断します。いずれこの
部分にはやたら英文の略語が多く理解の障害となっているのは事実です。
そして、Computer の中身を Computer 用語を使って使用しようとする
以上、一度はじっくり用語の意味を確認する事が大事でしょう。
Unit の中身は以下の構成部品で占められます。 MotherBoard CPU
ROM RAM Video-Board Power-Unit Disc-Drive だ
いたいこんな物でしょうか・・。
Mother-Board --> 他の Board を接続させる為の大型基板
CPU --> 中央演算装置、つまりは心臓部
ROM --> (R)ead (O)nly (M)emory = 読み出し専用 Memory
RAM --> (R)undam (A)ccess (M)emory = 読み書き可能 Memory
IO Board --> (I)nput (o)utput Board 入出力制御の基板
Video Card --> Monitor への信号出力基板
Power-Unit --> 電源 直流 12V (現在は 5V または 3.3V) に整流して供給
Disc-Drive --> Floppy Drive or HardDisc Drive
 現在ではなくなってしまった IO Board と
は Input Output Controler Board の事です。
意味からいって、入出力を制御、橋渡しする Board という事になりま
す。この Board には Floppy Disc , Hard Disc , RC232C , Mouse ,
Printer 等の別な装置の接続線がすべてつながれて一括操作されます。
もちろん MotherBoard に差し込みでつながりますから、当然 CPU ROM
RAM へもつながっていました。
現在ではなくなってしまった IO Board と
は Input Output Controler Board の事です。
意味からいって、入出力を制御、橋渡しする Board という事になりま
す。この Board には Floppy Disc , Hard Disc , RC232C , Mouse ,
Printer 等の別な装置の接続線がすべてつながれて一括操作されます。
もちろん MotherBoard に差し込みでつながりますから、当然 CPU ROM
RAM へもつながっていました。
昨今の機械は Mother-Board に埋め込まれてしまい、
現在の市販されている機械にはついていません。
Mother Board 上に合体してしまい上記のコネクターだけが整然と並ぶようになりました。
(すぐに現実を見たいという方は Click その後戻るには[戻る]ボタン)
Video-Card は Monitor との橋渡しをする Board です。
歴史的に進化してきた Board の為、たくさんの Video mode 形式があります。IBM 55** 等は
MDA であり、これ以後 EGA CGA VGA と発展、現在は SVGA XGA XGA-2
と各種 Board が主導権争いをしていますが、現在は SVGA から巨大画面への対応を含め、
大勢は大きく変わって 21inch monitor に対応、この先はさらに街頭の巨大 monitor に
対応へ向かっています。
この Card は時代を背景に差込するコネクターの種類が、その当時の Bus に対応するという
変遷をしたため、種類が多く ISA VL-BUS PCI AGP -> Express x16 と言われる差込形式と Video mode 形式と
をもって発展してきました。同じ SVGA でも Bus は PCI だったり AGP だったりします。
いずれも描画速度のアップのために自分自身の名称と、差込の形式とを変遷してきました。
今後の主流は AGP(現在のExpress) になるでしょうが、
業務用であれば PCI Bus で良いですし、Video Card の Memory は 2MB もあれば十分です。
ゲームなどをするという理由でない限りは 8MB もの必要など決してないと僕は思います。
( その差込の違いを見たいという方は Click )
| 年代 | IBM5550 | PC/AT 1993 | PC/AT 1995〜 | PC/AT 2000〜 | PC/AT 2001〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| OS | K-DOS2.7 | DOS/WIN3.1 | WIN95/98/NT | WIN98ME/ 2000 |
WIN XP |
| CPU | i8088 | 80486DX | PEN2 | PEN3 | PEN4 |
| MHz | 8MHz | 66MHz | 266MHz | 500MHz | 1.2GHz |
| MEMORY | 256KB | 16MB | 32MB/64MB | 64MB/128MB | 256/512MB |
| HDD | 8MB | 540MB | 2.1〜4.3GB | 10〜20GB | 40〜80GB |
| FDD | 5.25 FDD | 3.5 FDD | 3.5 FDD +CD-ROM |
3.5FDD +CD-RW |
3.5FDD +DVD-RW |
| CD-ROM | None | 2X | 24X/32X | 32X24X12 | 84X32X24 |
| VIDEO | ?? | 1MB | 4MB/8MB | 64MB | 128MB |
| BUS | MCA | ISA/VL-BUS | PCI/AGP | PCI/AGP | PCI/AGP |
| Clock | ? | 66MHz | 100MHz | 133MHz | 266MHz |
Power-Unit は当然
電源
の事です。現在の主流
は 150 〜 250W だと思います(2005年では平均 400W)。
Monitor への供給電源を内包しています。過去には 12V または
5V の直流を供給していましたが、現在は省エネで 3.3V のものに変化していますし、
最新鋭のものは 1.35V さらには note 用の Celeron 1.1V 又は 0.975V (バッテリー使用時)
という低電圧へ移行しようとしています。
従って、最新のものほどワット数は減っています。200W もあれば十分な時代になりました。
最新のものである ATX 仕様とこれまでの AT 仕様では Mother Board の
接続ネクターの形状が変化していますから注意は必要です。
( 両方の Connector をもっている Mother Board があります。どんな風に違うかを
知りたい方は Click AT ATX の Connector の差がわかります。
その後戻るには[戻る]ボタン)
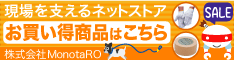
もっとも、21世紀になってからは、AMD が主力の CPU となり、実はこの CPU を
動作させるためには 400W 以上の電源が必要な時代になりました。
起動時にハンマー電圧という回路に必要な電気が大きすぎるようですが、CPU を
たたき起こすには必要なのでしょう。
Unit に載るものの代表は CPU です。いわゆる中央演算装置と訳され ていますが、業界では「石」とも呼び、そのメーカーは Intel AMD National Semiconductor(Cyrix) Motrola が代表格でしょう。Intel がもっとも先鋭的な開発投資をしています。 MotherBoard の基板の上で一番でかい真四角の「石」、それが CPU です。 上記の型式が印刷されているのですぐ判ります。
CPU は Central Processor Unit 中央演算装置と訳されます。色々の 処理をする電気的な回路を集約したもので、その図面は可視出来る サイズにすればサッカー場ぐらいの大きさになるのだそうです。この辺 は僕の知らない高度な部分なのでしょう。歴史的に Intel に限ると 8088 8086 80286 80386 80486 Pentium PentiumII 最新の Celeron PentiumIII 又は PentiumIV などと経緯したもので、 現在は個人の使用する CPU の中心は 266MHzで、 最近販売されている中心は 1GHz の CPU 、 さらに今後の主流は 1.6GHz になっていくでしょう。 しかし、266MHz もあれば体感速度に変化はありません。 これ以上の速度を求めても一般の方の利用には無意味だという側面もあります。
もちろん Intel 以外の互換 CPU も存在する訳で、最近は Mother Board との整合性もそれぞれ用に分かれてきました。 MHz というものが処理スピードのことであり、 機械全体の処理速度を決めると言っても過言ではありませんが、 最近は CPU の処理速度に追いつかない周辺機器の改良が頻繁です。 ペースクロック 100MHz や 133MHz (2001 には 200MHz が登場するだろう) という表示が増えてきました。 旧来の 66MHz と最新の 100MHz 133MHz との差は CPU に追いつかない周辺機器の改良です。 周辺の機器全部の最低スピードが 66MHz から 100MHz 又は 133MHz、 さらには倍速の 200MHz 233MHz 533MHz へ向かっています。 2009年になるとなんと 3200Mhz などという猛烈なスピードが現実となりました。 いわゆる、3.2GB ということになりますが、GUI というグラフィック画面を求めた われわれの希求の結果です。しかしながら、依然として ほとんどの処理を CPU が判断し、担当機器へ命令分配します。
MotherBoard は Unit の一番底に置かれているどでかい基板の事で す。 多分 Unit 一杯の面積を占有し、他の Board を差し込み連結させ るコネクターが多数ついています。あらゆる付帯装置はこの Board に つながって始めて動作する様になります。特に、IBM 互換機の場合は外 形寸法は完全に一致しており、どの機械にもセットできる様に厳密に互 換性を保っています。 しかし、1995 年までは国内の 日本 IBM を含む NEC (9801 9821) EPSON、 富士通 (FMV)等は新機種を投入するたびに上記の外形寸法を変更しており、性能の良 い機械を購入するには Unit 全部を購入する必要がありました。 国内では日本 IBM が最初に IBM 互換機の部品を採用し、現在各社は世界中で利用さ れている PC/AT と総称される基盤を採用しています。
*** この IBM PC/AT という規格は、MotherBoard の互換性をもって 周辺機器のあらゆる互換性を保証するという快挙にでたのはもう大昔の事です。 HardWare 廻りの情報をすべて公開するという USA IBM の 戦略は、市場を独占する為に展開された様です。 確かに新規参入したまね Board によって世界中が互換 Board で埋めつくされ、 市場は PC/AT という機械で独占されていますが、IBM はその主導権を握れませんでした。 むしろ、まねをして作成し、IBM より良い性能の互換機メーカーによって市場は動いていま す。最近の代表格といえば、 GIGA-BYTE 台湾の SOYO A-Open などで極東アジアが 電子機器の中心になってきました。最近の MicroSoft 社の USA に置ける独禁法違反容疑は健全な USA を示す格好の材料と言って良い と思います。独占は悪だ という基本理念が USA という国の姿勢なのだと思います。 われわれの国はどうでしょう?!。

歴史的に Drive 記号は装備された Disc Drive の数で設定されてきました。
最初は 5 inch Drive 1 ケの System であり、その Drive は [A] Drive としました。
次に Program が大きくなり、Disc 1 枚の Program になった時、
機械には 2 つ目の DATA Drive が追加されました。
Floppy Drive を 2 ケ持つ機械の登場です。
この 2 つ目の Drive は [B] Drive と名付けた訳です。
 しかし、さらに Program は大きくなって Floppy Disc に収納出来なくなった時、
救世主となったのはこの Hard Disc です。
容量が大きいこと以上にアクセススピードが早いので、あっという間に普及しました。
都合上、この Hard Disc には [C] Drive と名前が付けられたのです。
結果的には、Program や DATA はほとんど [C] DRIVE=Hard Disc に格納される様になります。
そして Floppy Disc は DATA の保管や移動を目的とする媒体に変化します。
しかし、さらに Program は大きくなって Floppy Disc に収納出来なくなった時、
救世主となったのはこの Hard Disc です。
容量が大きいこと以上にアクセススピードが早いので、あっという間に普及しました。
都合上、この Hard Disc には [C] Drive と名前が付けられたのです。
結果的には、Program や DATA はほとんど [C] DRIVE=Hard Disc に格納される様になります。
そして Floppy Disc は DATA の保管や移動を目的とする媒体に変化します。
*** Hard Disc = [C] Drive は IBM 互換機の場合は固定です。 たとえ [B] Drive が存在しなくても、Hard Disc は [C] Drive になります。 しかして、DOS/V の機械の場合は [A] と [C] の Drive のみが存在します・が、 実は Floppy Drive 2 台は同一の 50 線のコード 1 本で連結される為、 DIR B: と打てば [A] Drive は [B] Drive として誤認される様になります。
国産の NEC 9801 9821 等は System 起動 Drive が必ず [A] Drive になる様に Program 設定されており、起動 Drive の場所によって Drive 記号が変化します。 つまり、固定ではありませんから注意が必要です。 したがって正常な場合 PC/AT 機では [C] Drive 表示されるはず の HDD が [A] Drive 表示されるのが正常です。

Floppy Disc と Hard Disc の差は同様に記録媒体である事は同じ事なのですが、
現実の利用形態の統計はまったく別な事実を表出しています。
 |
*** 現在の 3.5 inch Floppy Disc の最大容量は 120MB というものもありますが、 特殊な Drive を購入する必要がありますし、高値の花です。
 今後の歴史が Floppy Disc の Program の記録媒体としての価値を奪うの
は確かな事です。CD-ROM は大量の容量を持ち、Program の様に読み込み専
用のものの場合は、CD-ROM の天下になるでしょう。ちなみに Compact
Disc Read Only Media (CD-ROM) と
いう意味は書き込み不能であるという
事であり、DATA 等を保管書き込みする事はできない機器です。
同様の言い回しが DVD-RAM±R/RW でも利用されています。
2006 年なって CD-ROM もその時代を終えたのかもしれません。
今後の歴史が Floppy Disc の Program の記録媒体としての価値を奪うの
は確かな事です。CD-ROM は大量の容量を持ち、Program の様に読み込み専
用のものの場合は、CD-ROM の天下になるでしょう。ちなみに Compact
Disc Read Only Media (CD-ROM) と
いう意味は書き込み不能であるという
事であり、DATA 等を保管書き込みする事はできない機器です。
同様の言い回しが DVD-RAM±R/RW でも利用されています。
2006 年なって CD-ROM もその時代を終えたのかもしれません。
ちなみに CR-ROM の M の意味を Memory と 訳している書物もあるようですが、完全な誤認の結果だと僕は思います。 Media と訳す方が将来にとっても混乱を防ぐ意味で良いと僕は思っています。 Memory とは記憶媒体なのであり、電源 OFF までは保持している内容のことだと僕は 思っています。間違った表示は出来るだけ早く修正されるべきものだと思いますが、 貴方はどう思うでしょうか・・。
 |

MotherBoard の隅に差し込みが 2 〜 4 つ並んでいるはずです。 Hard 的にはここに差されている部品が RAM です。( Mother Board を確認したい方は またも Click ) 1 つが 1MB 2MB 4MB 8MB 16MB 32MB 64MB 128MB 256MB などいろいろの容量がありますが、 、合計が保持している Memory ということになります。そうで す、最初の電源投入時に Monitor でカウントされる数字は RAM 容量の CHECK をやっている訳です。
RAM と
は Ramdum Access Memory の頭文字の略です。
一般には書き込み可能 Memory といわれます。非常に大事なもので、あらゆる Disc に
格納された Program や DATA 等はすべて Disc から RAM へ転送されて初めて
利用できる様になります。 Program の肥大化に伴って RAM 容量は次第に増
加し、最近の機械は WINDOWS を動作させる為に最低でも 16〜32MB の容量を
必要とします。( 安心したいのならば 512MB/WIN XP だそうです。)
実際に Memory を増加させると効果がどれほどあるのか紹介していますから
右下の IO Deta 社のビデオを見るのも参考になるかもしれません。

RAM がもっとも Computer 管理者を悩ませたものの代表です。機械自
体は、8088 CPU の頃は Memory も小さくてすみました。ちなみに 5550
は 256KB という容量でしたが、Program の肥大化はこれを転送する先であ
る RAM の増加を余儀無くし、容量は増大の一途を辿っています。
1024KB が実は Memory 管理の限界であった事はよく知られ
ています。 ここを突破する事がとても大変な事でした。 80286 という
CPU が初めて 1024MB の壁を越えます。これは MS-DOS という基本 Program
が Memory 管理の限界を 1024 に持っていた関係です。
簡単にいうと MS-DOS は根本的に Memory 番地の指定を 16 進法でや
っていて、その番地番号を 4 桁までとした事でできた限界です。16 進
法の最後を意味する FFFF という終着駅が 1024KB だった訳です。(***)
RAM は主 Memory (Convention Memory) =640KB 、UMB =640KB 〜1024KB
、 XMS=1024KB (EMS を含む) から上の領域に分かれます。この点は別の
付録の
MS-DOS SYSTEM - 起動からプロンプトまで
で図示しています。
 また、memory の HardWare check Program も存在します。
memtest86は
Linux 系列の SoftWare ではありますが DOS & Windows 版が存在します。
Gnu Public License (GPL) であり自由に利用できる。
動作中の停止が頻繁であれば、チェックするのは安心確認の上で需要です。
僕自身が、上記の事態でチェックを試みたからです。
また、memory の HardWare check Program も存在します。
memtest86は
Linux 系列の SoftWare ではありますが DOS & Windows 版が存在します。
Gnu Public License (GPL) であり自由に利用できる。
動作中の停止が頻繁であれば、チェックするのは安心確認の上で需要です。
僕自身が、上記の事態でチェックを試みたからです。
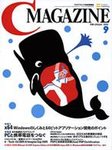 *** 16 進法については、0123456789ABCDEF という記号で表示される
数字です。10=A 11=B...15=F と表示されます。16 になって初め
て桁が上がり 10 になります。1B は 10 進法でいくつでしょう
か・・。 10=16 B=11 ですから 27 です。難しいですね・・。
Computer 関連雑誌には「256 倍楽しむ方法」 なんてのが結構あ
りますが、 10 進法の 256 は 16 進法で 100 になる洒落です。
この表示法はまさに Computer の為に考案されたものであり、電
卓からはては Super-Computer まですべての電子機器で利用され
ています。
*** 16 進法については、0123456789ABCDEF という記号で表示される
数字です。10=A 11=B...15=F と表示されます。16 になって初め
て桁が上がり 10 になります。1B は 10 進法でいくつでしょう
か・・。 10=16 B=11 ですから 27 です。難しいですね・・。
Computer 関連雑誌には「256 倍楽しむ方法」 なんてのが結構あ
りますが、 10 進法の 256 は 16 進法で 100 になる洒落です。
この表示法はまさに Computer の為に考案されたものであり、電
卓からはては Super-Computer まですべての電子機器で利用され
ています。
つぎに ROM ですが、単に ROM と漢字 ROM とがあります。漢字 ROM
は乗っていたり、乗っていなかったりで色々です。ちなみに、NEC 9801 9821 FM-TOWNS など
過去の機種には載っています。
乗っていない国内メーカーは NEC を除いて [V} の記号がつく場合が多いのでわか
り良いですが、NEC は PC98 から乗っていません。
IBM(PC)-DOS 6.1/V は漢字 ROM がなくても良いのですが、
日本 IBM 系は載っているとの雑誌の話です。
ROM とは Read Only Memory の頭文字です。
読み出し専用 Memory と訳されます。
いずれも非常に小さな Chip になって Mother-Board の上に乗っています。
漢字 ROM Chip はスピードアップの為に漢字 CODE 表を焼き付けて所有してお
り、高速に表示させる事ができます。
![]() Keyboard は
とても影武者です。実は Monitor との橋渡しをする大事
な物でありながら、もっとも軽視されてきたものの一つでしょう。HomePage
Book の中でも制御文字の記述で述べましたが、Keyboard の色は白と灰で実は制御
文字であるかないかを区別しています。 貴殿が白色の Key を押した場
合は何の問題もありませんが、灰色の Key 、特に CTRL SHIFT ALT(前
面) Key 以外の Key の場合は押すだけで直ちに制御文字が入力される
可能性があります。(灰色 key の詳細へ)
Keyboard は
とても影武者です。実は Monitor との橋渡しをする大事
な物でありながら、もっとも軽視されてきたものの一つでしょう。HomePage
Book の中でも制御文字の記述で述べましたが、Keyboard の色は白と灰で実は制御
文字であるかないかを区別しています。 貴殿が白色の Key を押した場
合は何の問題もありませんが、灰色の Key 、特に CTRL SHIFT ALT(前
面) Key 以外の Key の場合は押すだけで直ちに制御文字が入力される
可能性があります。(灰色 key の詳細へ)
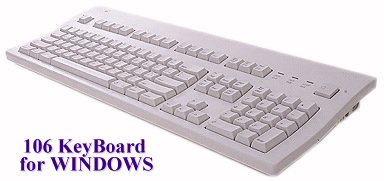
Mouse は同様の意味で ワープロ (EX. MS-WORD) 上では文字入力以外
を担当する関係で、WINDOWS ワープロ 上ではほとんどの場合は制御文字
を入力する場合に利用されます。ワープロ 以外では操作性の向上を狙っ
ており、Key Board に比べればその機能は簡単かつ便利です。
右 click から、最も利用する CUT & PASTE はその便利さにおいては、これまでの操作が信じられないくらい昔のことに思えるほどです。
所で Mouse-Pad という道具がありますが、これは大事なものです。
Mouse の構造は内部にボールがあり、ケースの上部にこのボールに密
着するローラーが 3 ケ、ポールの動きをこの内の 2 ケで電気的に解析
して Monitor の Cursol を動かしています。1 ケはダミーで支えの役
割です。Mouse が壊れるのはこのローラーにゴミが付着する為で、僕
などはこの 2 年の間に 2 ケ壊しました。Mouse Pad を使っていてもこ
の現実です。
動きが悪くなったと思うならば、マウスのボールを取り出して
上記の三箇所のゴミを取り除くことでこれまでの動きに戻ります。
僕は年間に五回以上は上記のゴミ取りを実施しているわけで、
このことは、機械であることを立証するハードウェアの特性だと思います。
一度は、中身を見てゴミの確認を推奨します。
平らであることがローラーの破損を防ぎます。
町中のパソコンショップへ行けば、
Pad は \1.000 -程度で販売されてい
ます。購入するべきものです。ちなみに動きの悪い Mouse は、
ローラーに付着したゴミを取り除くことで改善されます。
2009 年の 2 月に僕は形成外科へ通うことになった・。理由は右ひじに血がたまるのだ。 医者のいう話ではパソコンのやり過ぎとの診断になった。確かにこの一年の僕は、会社の Note を机の一番奥において仕事をしていた。何せまだ紙の処理が多いから紙の置く場を 確保すればパソコンは一番先奥にしてしまう愚考をしてしまった。両ひじが机の上ですれていた。 特にマウスを利用する右は酷使されたのだと思う。回復に向かっていると思う僕だが、 現在はひじは空中に浮いて利用できるように機械を移動させた。 同じ過ちをしないように、この web を見た人には告白しておくことにする。

|
*** 余談になりますが特殊だと思っていた日本 IBM の 5577 Printer Mode は HardWare の変更ボタンを利用しないでも、 DOS Mode であれば 実は SoftWare で変更できます。 5577 導入の際に付属して いた Printer Utility Disc の SoftWare を導入すれば、 Computer 画面から Printer Mode を変更して ESC/P に出来ます。 残念ながら、この事は導入しなければ利用できないという結果です。 ESC/P しか対応しない Program を利用する必要が個人的にあったので僕は利用しています。 いずれ導入する必要がなければ、なくても良いものです。
|
|

*** あくまでも MS-DOS 上の話ですが、TEXT FILE であれば制御 文字を含まない為、Mode に関係なくあらゆる Printer で印刷で きます。 ワープロを利用するとそのワープロの指定出来る、 Printer でなければ印刷できないという・・またしても機種互換 のない制御文字の規定に縛られる事になります。
*** 上記の 9600 とは 9600 BPS の意味で毎分 9600 bytes の 文字を送受信できるという意味です。Bytes Per Second ス ピードを表示しています。最近は 57K または 64K がよく利用されています。
 エレコム海外用変圧器
エレコム海外用変圧器trans pal 120【T-TP120】送料無料 |
*** MNP4 とは MICRO-COM 社の提唱した Error Free System の事で Modem が Check を 実施する機能をもったもので MNP1 2 3 4 5 6 5 7 8 9 10 までの 規格が ISO 90 として認知されています。 現状の個人通信の場合の平均は MNP5 であり、自分の方だけランクを上げても、 接続する方がそれより低ければ自動的に両者の対応する LEVEL へ下げて接続されます。 これは FAX の G3 G4 の扱いと同様です。( 携帯電話の場合は MNP10 です。)
Modem は現在 FAX 機能を加算されて \10.000-
を切って販売されています 57600 BPS で 9600 BPS FAX 付きが平均という所です。
Modem に FAX は付属して当然の機能になりました。Computer を利用すると、
SoftWare 的に電話回線を FAX 付きにしてくれます。
それは Modem の持っている FAX 機能のおかげです。
つまり Computer を所有する人は Hard 的に FAX 機器を買う必要はなくなったのです。
FAX 付き Modem は通常の電話回線用の FAX を購入した事と同じ意味を持ちます。
しかし、価格は雲泥の差です。
また、電話線を経由せずに Ethernet-Card というものが
今や当たり前の様にパソコンショップの店頭にならぶ様になりました。
電話線を経由しないで 2 台以上の Computer をつないでしまうという発想は
その要求度の高い、職場での利用が先頭を切っていましたが、
ここへ来て 2 台目を家庭で利用することも当然になってきたようです。
それぞれの Ethernet-Card で連結された Computer の data file を共有すると
いうことで、各 Computer のそれぞれの利用者は一方の機械で
他方の機械の保管 data や Program を動作させることが出来るようになるので、
SoftWare を含む情報の共有化が成立することになります。




一般的には peer to peer、10base-T (10Mbps)、100base-T (100Mbps)、10base-2(HUB間)
などと分類がありますが、いずれ事業所等でたくさんの Computer がある場合は、当面は
Backup などの目的には重宝なものであり、また保管 Disc を大容量にできるという
利点もあります。もちろんルールを決めて保管しないと大量の各 Computer のどこに
保管したのか不明なんて笑えない事態になる場合もあるので、構築時点でしっかり
ルールを決めることが肝要だと思います。
このルール部分をしっかり構築すると、情報という
ものが Computer を経由した利用に変わっていくのだそうです。なぜってこれまでの
Floppy Disc をもって走り回る( Sneaker Network = Network の最下層形態 )
なんて事をしなくて良くなるからで、そんな面倒なことをしなくて良いと知ったら、
もう copy の為の空 Disc を探す必要がないと知ったら、
僕など歓喜してしまうかもしれません。
なにせ読める Disc と読めない Disc 、その煩雑さから
開放されたいと思っているのは僕だけではないと思う。
さらに Bluetooth 対応という規格が一般化しようとしている。
たくさんの機械が接続されると配線という煩雑さがあるからだ。
無線 LAN の一種であるこの規格は接続線が皆無だという意味では
今後の注目すべき規格となっていくと思います。
また、Ethernet に ADSL Modem を接続して Intrenet 経由で連結させる
事は 2004 年に爆発的に普及しました。現在はほとんどこの形だと思います。
スピードが速いため、画像や音楽、video などの送受信には合致していました。
LAN card を利用したシームレスな環境を構築するという古くからあった発想が、
電話代という対価まで破壊していくのかもしれません。ようやっと、分散する computer
の data の共有へ向かい始めたようです。YAHOO BB! が実は Internet の新しい環境
を構築していくことになりそうです。なぜなら、なんだ隣の機械も連結できたんだとい
う事実を示すことになるからです。連結のひとつの形式が BroadBand に過ぎなかったと
たくさんの人々が 2003 年になって大合唱することになると思います。
Router という機器が店頭にも並ぶものになりました。以下の設定に必要な道具といえます。
24 時間 Computer の電源を入れっぱなしで、この Computer の Internet address を習得、
さらに Router をセットして WebPage を提示できるようにする。これでこの機械はまさに
Internet Site になってしまう。つまり Provider などなくても Internet 環境を構築できる。
このことは「通信傍受法案」がいかにザル法なのかの証明になってしまうと思う。僕が上記を実現
したとしよう。僕は Provider ではないのだから通信記録を取る義務もないし、送受信する
Mail の記録もいらない。みんなが同様の Site を構築すれば、傍受なんてできっこない
と僕は思う・。
結局、多くの大企業は上記の方式を取ることが安上がりなのだ。
大手はみんな自社の名前の
co.jp ( Company Japan の意味だ )という Site 名になる様に HardWare 環境を整えている、
つまり各社は自分で Router を利用している Provider と同じ立場にあるということだ。
「通信傍受法案」が取り締まるのは、僕らのような Provider 経由の個人の記録だということになる。
対価を惜しんでやっと利用している弱い立場の個人を取り締まる法律だといっても過言ではない。
組織犯罪を本当に取り止まれるのか良く考える必要があると思うのは僕だけだろうか・・。
 |

|
|

|
また Scanner に限ったことではないが、翻訳という技術 の進歩は急ピッチに進んでいる。FreeWare Babylon は さまざまな言語間の単語翻訳を画面上で実行してくれるし、英単語の発音まで確認 出来る。
|
|
 |
最近はあまりに利用者にあわせた OS が提供されるようになり、 Computer の 根本は理解しなくても良いという風潮を助長する事態になった。が、実態は 違う。2009年の夏、CD-ROM の内容を別な CD に焼きつかせようとした新人の社員の 発言に呆れた・。安くなくとも、焼くという言葉を使う CD の製作は Copy&paste とは 違うことが理解されていない。つまり、copy できないので drive である CD drive が 壊れているという発言があった・・。
残念ながら、CD の copy は一旦、豊富な memory や HDD にデータ転送されてその上で新しい CD に書き込まれることを理解していなかった・・。 この場合は、HDD の残っている残領域は CD より小さかった・・、 残念にも、悲劇的にもこの状況では決して新しい CD を製作できない。 根本的な仕組みの理解の欠如は、この先の勉強をしていない若い人にはお灸になるのか、 或いは、僕の方にオタクである人間が異常だといわれる時代がまだ続くのかと わが耳を疑ったことを書き添えておく。 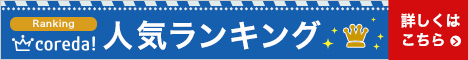

すでにネガのある写真は実は簡単にデジタル化する手段がある。国内では 熱心な宣伝がされていないのが理由だろうけれど KODAK Phote-CD という方法だ。 KODAK という看板のある写真屋さんで取り扱っている。100 枚の容量を持つこの CD-ROM は写真のネガから次々にデジタル写真を追加できる。 対価を安くかつ手っ取り早くと思う人は試した方が良いと思う。
僕も最初はこれを多岐に利用した。なにせ元々の写真ネガの 精度が高いのだから、もっとも画素の多いこの方法が鮮明さではダントツだと思う。 Data File 名は ****.PCX という名前で他の目的のために移動させて利用することも 可能だ。標準の Windows は読みこみ可能だと思う。 現在(2004)では、Digital Camera の CD-R 転送操作をパソコンなしで 実現できる HardWare も出現している。 ヤケルくん「GH-YKR48」 という 名前通りの簡単機器である。
もっとも、時代は進んで一般の写真プリントも Internet 上で実現できるようになった。 富士フィルムが始めた 多画面タイプのプレミアムポストカード
など、デジカメでプリントは上記の逆襲と言えるかもしれない。
3 つの HardWare は一台でできるはずたという発想があなたにあるだろうか。 Printer Scanner Fax 全部を可能にする複合機材は Lexmark社によって 2001/6 に成立した。しかも価格は 2 万円を切っている。2002 年の後半には Canon が、 さらに color copy 機能を追加した汎用機を販売した。Printer も computer の一部で あることから遊離しはじめた・・。


 |
*** Interrace というのはまず奇数走査線を refresh して、 次に偶数を refresh するというやり方で、 画面のちらつきが多かった訳で、 これを改善する為に考案されたものが Non-Interrace です。 WINDOWS の登場で一躍 Monitorの中心に座るものになりました。 refresh が 123456 の走査線順に実施されます。*** 15 inch Monitor で 1024 X 768 では文字が小さすぎます。 Large Font を利用すれば 良いのですが、それでは WINDOW の size が大きすぎる事になり、Font 選択が結構大変です。 17 inch が当然のように普及した背景だと思います。

OS= Operation System の事ですが、すでに CP/M MS-DOS MS-WINDOWS という OS は存在し、 歴史的な使命をそれぞれが果たして来た訳です。 DOS WINDOWS の詳しい説明は MS-DOS の説明に譲るとして、 WINDOWS の媒体連結は凄い速度で整備されています。 前述の Addin TV もその一つであり、 入出力関係の HardWare がどんどんと発表され、 まさにKeyboard からの遊離に向かっています。 しかし、それらはやはり OS の System によって制御され装置としての主張をしている訳で、 お互いに必要な HardWare SoftWare を並列的に出現させています。 OS とは HardWare を連結させる為の唯一つの指令塔に他なりません。
WINDOWS は現有の指令塔としては最新の System であり、
その WINDOWS を動作させる為に他の Hard が開発されて来たというが事実です。
ここまで説明してきた CPU の処理速度の改善、大容量の Hard Disc、
大型の SoftWare を動作可能とする RAM の巨大化、Text Mode から Graphic Mode への大転換、
いずれもここ 10 年の間に激変したといっても過言ではありません。

 MAC が実現していた GUI ( Graphic User Interface ) という
思考が MS-DOS には欠けていました。基本的な OS への命令を Keyboard 以外から出来ないか。
これが最初の開発に取り組んだ
ゼロックス社の出発点であったとの事です。それは
枝分かれして現有のたくさんの OS となっています。WINDOWS 以外にも UNIX の X-WINDOWS や
OS-2 WARP などいずれも Mouse を利用した Click を利用するやり方になっているのは、
その出発点の発想の賜物だと思います。
MAC が実現していた GUI ( Graphic User Interface ) という
思考が MS-DOS には欠けていました。基本的な OS への命令を Keyboard 以外から出来ないか。
これが最初の開発に取り組んだ
ゼロックス社の出発点であったとの事です。それは
枝分かれして現有のたくさんの OS となっています。WINDOWS 以外にも UNIX の X-WINDOWS や
OS-2 WARP などいずれも Mouse を利用した Click を利用するやり方になっているのは、
その出発点の発想の賜物だと思います。

また、これらの最新の OS たちは、導入された機器を自動的に検索し利用できるように
するという Plug & Play という装備を持つに至り、導入の設定という煩雑さから
僕らを解放しました。 GUI としては、ほとんど完成したといっても良いでしょう。
Computer は実はプレーヤーにもなりうるのだという発想は、音楽の知的所有権にも多大な
営業を与えました。いまや音楽も digital 化され、contents のひとつと化したのかもしれません。
音楽CD はいまや町のレコード店で購入するものではなくなったのだと思います。

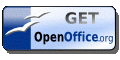 最近の上記の Program はいずれも HTML File として保管する
(Web Page として保管する) という保管形式を
持っている事に気がついているでしょうか・・。保管の際にじっくり Pulldown Menu を
みると発見できるはずです。なぜこの形式の保管がすべての文具にあるのでしょう・・。
なぜだとおもいますか・・。
最近の上記の Program はいずれも HTML File として保管する
(Web Page として保管する) という保管形式を
持っている事に気がついているでしょうか・・。保管の際にじっくり Pulldown Menu を
みると発見できるはずです。なぜこの形式の保管がすべての文具にあるのでしょう・・。
なぜだとおもいますか・・。
つまり、僕らはやがて「保管はすべて HTML File でするように」という通達を受ける場面に遭遇する事になるでしょう。
あらゆる SoftWare がそのことでもって互換性を保持できるようになるからです。
そして、この形式は情報公開というあたらしい路線の標準となっていく事でしょう。
知らなかったと貴方が思うならば、たった今から今後は HTML 形式で保管をすべ
きです。少なくとも、MS-WORD の専用 File (*****.DOC) なんて File で
保管はしないことです。
それがその文書の公開と継続利用に道を作っていくことになるでしょう。
他の人に利用されない data なんぞ何の価値があるでしょうか・・、
貴方と僕の考えは同じだと良いのですが・・。
上記の HTML File には link という配慮が欠けています。つまり関連 File へ飛ぶという
青色の文字列です。上記の HTML File を総合的に管理し、関連 File を Web すると
いう考えの下で文書を管理するという会社が増えているのだそうです。さらに進むと、
各所轄で作製された HTML File を他所轄から閲覧した場合は口銭を取るというシステム
にしてしまったところもあります。確かに情報はタダではないということも事実と言え
ば事実ですから・・。
上記が必要な情報を丸ごと受け取るという WWW (World Wide Web) と
まったく同じものです。
実は、Internet のこの方式は、電話線などなくても企業などの大規模システム内で
同様に利用できるという事です。もっともその青色の文字を挿入してどこへ飛ばす
かという事を専門に挿入する人が必要になるのかもしれませんが、ルールを先に作って
置くことが先決だと思います。
2000/Jan AOL(America On Line) とタイムワーナーが対等合併しました。もちろん前者 は世界最大の NetWork provider であり、後者は CATV網を利用して CNN という NEWS を 提供している。同時に AOL は AOL TV という端末を発表しました。つまり TV であって Internet 端末という機材が登場したことになり、ここで採用されている HD (Hard-Disc) はなんと 20 時間の録画が可能という事実があります。もともと HDD の Backup として 利用された TapeDrive 、考え方を逆転させれば VidoeTape の変わりに HDD をという事 なのでしょう。(しかし 20 時間も録画したものを見るほうも大変だ!)


 
|

|
|
| IRQ | 9801(INT) | 9821(INT) | 利用機材 |
|---|---|---|---|
| 0 | * | system Timer | System timer |
| 1 | * | Keyboard | Keyboard |
| 2 | * | CRTV | Controller IRQ 8-15 |
| 3 | 0 | * | COM2 |
| 4 | * | COM port | COM1 |
| 5 | 1 | * | LPT2 (for SoundBraster or E-IDE) |
| 6 | 2 | * | Controller for FDD |
| 7 | * | Controller IRQ 8-15 | LPT1 for Printer |
| 8 | * | ODP | System CMOS |
| 9 | 3 | Controller IDE harddisc | * |
| 10 | 41 | 640KB FDD controller | * |
| 11 | 42 | 1.2MB FDD controller | * |
| 12 | 5 | Sound board | PS/2 Mouse 使用していなければ空き |
| 13 | 6 | Mouse | ODP (数値演算 processor) |
| 14 | * | Printer port | Cotroller for IDE |
| 15 | * | System Timer | * |
to the next page..めくる。
